耐震補強工事の費用相場と助成金制度をご紹介
日本は地震が頻繁に発生し、特に南海トラフ地震のような大規模な地震の発生が懸念されています。
このような地震活動があるため、耐震補強工事は特に重要です。費用感と助成金制度について、この背景を考慮した情報を提供します。
日本では地震が頻繁に発生し、南海トラフ地震などの大規模な地震が予測されています。このため、建物の耐震補強工事は非常に重要です。
耐震補強工事の費用相場は、地域や建物の種類によって異なりますが、1平方メートルあたり10,000円から20,000円程度が一般的です。
具体的な工法や補強の必要度によって費用が変動します。
しかし、この費用を抑えつつ建物の地震に対する安全性を向上させるために、助成金制度の活用がおすすめされます。
日本の自治体や国は、耐震補強工事にかかる費用の一部を補助するための助成金制度を提供しています。
この制度を利用することで、工事費用の負担を軽減できます。
特に地震活動が活発な地域や古い建物のオーナーにとって、助成金制度は大きな支援となります。
助成金の詳細な条件や申請方法は、各自治体や関連機関のウェブサイトで確認できます。
当記事では、耐震工事に関心のある方に向けて基本情報から助成金の活用までをまとめていきます。
目次
耐震補強工事とは
耐震補強工事は、建物や構造物の地震に対する耐震性を向上させるための工事です。これは、地震の際に建物が損傷しにくくし、人命を守るために重要です。具体的な工程には、建物の強化、補強材の追加、地盤改良、構造部品の交換などが含まれます。耐震補強工事は、法的規制に従って行われ、専門家の設計と施工が必要です。地震が頻繁に発生する地域では、建物の安全性を確保するために頻繁に行われます。
耐震補強と耐震診断の意味とは
耐震補強とは
耐震補強は、既存の建物や構造物の地震に対する強度や耐震性を向上させる工事や措置です。これは、古い建物や地震のリスクが高い地域で特に重要です。耐震補強は、建物の構造を改善し、地震の際に建物の崩壊や大きな損傷を防ぐことを目的とします。具体的な方法は、補強材の追加、柱や梁の強化、基礎の改良などが含まれます。
耐震診断とは
耐震診断は、建物や構造物の現在の地震耐性を評価するプロセスです。専門家が建物を調査し、その構造や材料の状態、地盤条件を評価し、地震に対するリスクを判定します。耐震診断の結果に基づいて、建物の現在の耐震性や必要な補強工事についての情報が提供されます。これにより、建物のオーナーや管理者は、必要に応じて耐震補強を計画できます
一般住宅と木造住宅の耐震補強とは
一般住宅の耐震補強
一般住宅は、コンクリートや鉄骨などの構造材料を使用した建物のことを指します。耐震補強は、この種の建物に対して地震に耐える力を強化するために行われます。具体的な耐震補強方法は、鉄筋コンクリートの柱や梁の強化、補強材の追加、基礎の改良などが含まれます。一般住宅の耐震補強には、建築士や構造設計の専門家の協力が必要です。
木造住宅の耐震補強
木造住宅は木材を主要な構造材料とする建物であり、耐震補強はその特性に合わせて行われます。一般的な木造住宅の耐震補強方法には、以下のようなものがあります。
壁補強
壁の補強により、建物の側面に耐震力を付加します。これには、クロスブレースや補強材の追加が含まれます。
基礎の改良
基礎部分の補強や改良により、建物全体の安定性を向上させます。
屋根補強
屋根の補強や増強により、地震時の安全性を向上させます。
木造住宅の場合、地震に対する耐性を高めるために、建物全体の構造に対する改良が行われます。耐震補強は、建物の形状や地域の地震リスクに応じてカスタマイズされ、建築士などの指導のもとで実施されることが一般的です。
建築物の基礎や主要部分の耐震補強
基礎の補強
ベース・アイソレーション: 地震時に建物を揺れから遮断するために、ベース・アイソレーションシステムを導入することがあります。これは、建物の基礎の下に設置された支持機構で、地震時に地盤と建物の振動を分離させ、建物への地震の影響を軽減します。
基礎の増強: 基礎の強度を高めるために、新しい基礎の追加や既存の基礎の改良が行われることがあります。これにより、建物が地震に耐えやすくなります。
主要部分の補強
柱と梁の強化:
建物の柱や梁は、地震の力に対して重要な要素です。補強材の追加、新しい柱や梁の設置、または既存の柱や梁の強化により、建物の構造を強化します。
クロスブレース:
クロスブレースは、建物のフレームに設置される斜めの補強材で、地震時の水平方向の力を分散させる役割を果たします。これにより、建物の揺れを制御し、構造の安定性を確保します。
壁の補強:
壁を補強することで、建物の側面に対する地震の影響を軽減できます。これには、壁に補強材を追加する方法や、壁自体を強化する方法が含まれます。
築40年、築50年の建物の耐震補強必要性
築40年や築50年の建物については、その状態や地域により必要性が異なります。しかし、一般的には以下のポイントを考慮することが重要です。
地震リスク
建物の地理的な位置による地震リスクが高い地域では、古い建物でも早い段階で耐震補強が必要となることがあります。
建物の構造
建物の構造タイプにより必要性が異なります。特に、木造建物や軽量鉄骨造の建物は、耐震補強がよく必要とされます。コンクリートや鉄骨の建物は一般的に強靭であり、長寿命を持つことができます。
建物の状態
建物の現在の状態が重要です。劣化や損傷が進行している場合、それらの問題を修復し、耐震補強と組み合わせることが必要です。
建物の用途
建物の用途も考慮すべき要因です。住宅や一般的な商業施設よりも、公共施設や病院などの重要な建物は、より高い耐震要件を持つことが一般的です。
地方の法規制: 地域や国によって異なる建築基準や法規制が存在します。現地の建築当局や法律に基づき、建物の耐震補強が必要かどうかを判断する必要があります。
耐震補強工事の方法と種類
耐震補強工事は、建物の地震に対する安全性を向上させるために行われます。この工事にはさまざまな方法と種類が存在し、以下にその概要を示します。
各種工法の特徴とノウハウ
ファミリー工房の耐震工事にはさまざまな工法があり、それぞれの特徴とノウハウが重要です。以下に、いくつかの主要な工法とそれらの特徴、ノウハウについて説明します。
基礎補強
特徴: 建物の基礎を補強して地震時の安定性を向上させる方法。
ノウハウ: 適切な基礎診断と補強材料の選択が必要。基礎の強度を向上させる際、適切な補強材料と施工技術を用いることが不可欠。
柱や梁の補強
特徴: 柱や梁の強度を増加させ、建物の耐震性を向上させる方法。
ノウハウ: 構造の設計と材料の選定が重要。構造要素の強度を適切に向上させることに技術と知識が必要。
耐力壁の設置
特徴: 耐力壁を設置して、建物の揺れを制御し、地震時のダメージを軽減する方法。
ノウハウ: 耐力壁の適切な位置と設計が必要。耐力壁の効果的な配置と設置が技術と経験を必要とします。
金物補強
特徴: 金物や補強具を使用して、構造要素を結びつけ、地震に対する耐性を向上させる方法。
ノウハウ: 適切な金物の選定と取り付けが不可欠。金物の正確な設置が補強の効果を高めます。
耐震補強材の利用
特徴: 軽量かつ強力な耐震材料を使用して、建物の強度を増加させる方法。
ノウハウ: 耐震補強材の適切な選択と施工が必要。補強材料の特性を理解し、効果的に活用する必要があります。
ファミリー工房の専門家は、建物の現状と地域の地震リスクに合わせて適切な工法を選択し、適切なノウハウを持って施工を行います。耐震工事は専門的な知識と経験が必要であり、地震に対する高い安全性を確保するために重要な役割を果たします。
免震と制震の違い
免震と制震は、地震時に建物や構造物の振動を制御し、被害を軽減するための耐震技術であり、以下にその主な違いを説明します。
免震とは
概要: 免震技術は、建物を地震の影響から切り離し、地盤との接触を制限する方法です。建物は基礎の下に設置された免震装置(基礎断熱材)に支えられ、地震時には建物が相対的に静止し、地盤の揺れを受けにくくなります。
特徴: 免震により、建物は直接的な地震の影響を受けず、振動が低減され、建物内部における被害を最小限に抑えることができます。
適用: 主に高層ビルや大規模な建築物に適用され、長周期の揺れに対して効果的です。
コスト: 免震技術は高コストかかり、建設および保守が複雑で専門知識を要します。
制震とは
概要: 制震技術は、建物に制震装置(ダンピング装置)を導入し、地震時に建物の振動エネルギーを吸収・制御する方法です。制震装置は通常、摩擦、粘性、ばねなどを組み合わせて構成されます。
特徴: 制震は振動エネルギーの吸収と制御に特化し、地震に対する反応を緩和します。建物の振動を制限することで、被害を最小限に抑えます。
適用: 制震技術は多くの種類の建物に適用され、地震の各種振動に対して効果的です。特に耐震性を向上させるのに適しています。
コスト: 制震技術は一般的に免震よりも費用が抑えられ、比較的容易に設置できます。
免震は建物を地盤から切り離して振動を減少させ、制震は振動エネルギーを吸収・制御して建物の振動を制限します。どちらの技術を採用するかは、建物の種類、地域の地震リスク、予算などを考慮して選択されます。
住みながら施工可能な工事方法
住みながら施工可能な耐震工事方法には、建物の住民が快適に暮らしながらも地震の安全性を向上させるための方法があります。以下にいくつかの方法を紹介します:
内部補強
特徴: 住人の生活に最も影響を与えない方法の一つで、主に内部構造の補強を行います。例えば、壁や天井に補強材料を追加し、柱や梁を強化します。
外部補強
特徴: 建物の外部に補強構造を追加する方法で、住人にはあまり影響を与えません。典型的な例は外壁に補強材料を追加することです。
耐震補強材の利用
特徴: 軽量かつ強力な耐震補強材料を使用して、建物の強度を増加させる方法。これらの材料は内部または外部に設置できます。
部分的な工事計画
特徴: 工事を段階的に実行し、住人が建物内での生活を続けるための計画。一度に全ての補強工事を行わない場合、適切な順序とスケジュールが重要です。
部分補強と全体補強、目安となる年数
| 特徴 | 部分補強 | 全体補強 |
| 定義 | 建物の一部に対する補強工事。 | 建物全体に対する補強工事。 |
| 対象 | 特定の構造要素や部分的な領域。 | 建物全体の構造体や基礎。 |
| 目的 | 地震時の耐性を向上させる。 | 地震時の耐性を全体的に向上させる。 |
| 費用 | 一般的に全体補強より低い。 | 一般的に全体補強より高い。 |
| 施工期間 | 一般的に短い。 | 一般的に長い。 |
| 住民の影響 | 部分的な工事なので住人の生活に比較的少ない影響。 | 全体的な工事なので住人の生活に大きな影響。 |
| 目安となる年数 | 建物の寿命を延ばすために10年から20年ごとに実施。 | 建物の寿命を延ばすために20年から30年ごとに実施。 |
旧耐震基準と新耐震基準の違い
旧耐震基準
施行時期: 旧耐震基準は、1981年から2000年代初頭までの間に施行された。地域によって異なるバージョンが存在する。
設計哲学: 旧基準では、主に建物の倒壊を防ぐことに焦点が当てられ、地震時の人命を守るための最低限の要件が設定された。
基準の厳格さ: 旧基準は新基準に比べて緩やかで、地震に対する建物の性能を確保するための要件が低かった。
更新頻度: 旧基準は年数十ごとに見直されることが一般的で、地震の最新研究と知見に追従しきれていなかった。
新耐震基準
施行時期: 新耐震基準は、2007年以降に段階的に施行され、地域による異なるバージョンがある。最新のバージョンはより厳格です。
設計哲学: 新基準は、建物の倒壊を防ぐだけでなく、地震に対する耐性を向上させることに焦点を当て、建物の被害を最小限に抑えることを目的としています。
基準の厳格さ: 新基準は旧基準に比べて要件が厳格で、地震時の建物の性能を向上させるための技術と材料の進歩に基づいています。
更新頻度: 新基準はより頻繁に見直され、最新の地震工学と建築技術に基づいています。地域の地震リスクに合わせて要件が更新されます。
新耐震基準は、地震に対する建物の安全性と耐性を向上させるために設計され、建築物の新規建設および既存建物の改修に適用されます。既存の建物についても、改修が必要な場合、新基準に準拠することが奨励されています。
耐震補強工事の費用相場と対策
耐震補強工事の相場費用は部分補強10万円から、全体補強100万円からと内容により大幅に予算が変わってきてしまいます。おおよその相場感と対策を解説していきます。
| 項目 | 部分補強の費用相場 | 全体補強の費用相場 | 補修費用相場 |
| 一戸建て住宅 | 500,000円から2,000,000円以上 | 1,000,000円から5,000,000円以上 | 100,000円から1,000,000円以上 |
| 地理的位置 | 地震リスクにより変動 | 地震リスクにより変動 | 一般的に地域により変動 |
| 建物の年数 | 建物の状態により変動 | 建物の状態により変動 | 建物の状態により変動 |
| 補強方法 | 部分補強によって異なる | 全体補強によって異なる | 補修の種類によって異なる |
| 専門家のコンサル | 建築家、構造エンジニア | 建築家、構造エンジニア | 建築家、修理業者 |
| 助成金/補助金 | 地域によって提供 | 地域によって提供 | 一般的に補助が提供されない |
1981年以降の建築物の改修費用の安全対策
1981年以降に建設された建物の改修費用は、耐震補強やその他の安全対策を含むさまざまな要因に依存します。以下は、建築物の改修における安全対策と一般的な費用対策の例です。
| 項目 | 部分補強の費用相場 (円) | 全体補強の費用相場 (円) | 補修費用相場 (円) |
| 一戸建て住宅 | 55,000円から220,000円以上 | 220,000円から550,000円以上 | 11,000円から110,000円以上 |
| 地理的位置 | 地震リスクにより変動 | 地震リスクにより変動 | 一般的に地域により変動 |
| 建物の年数 | 建物の状態により変動 | 建物の状態により変動 | 建物の状態により変動 |
| 補強方法 | 部分補強によって異なる | 全体補強によって異なる | 補修の種類によって異なる |
| 専門家のコンサル | 建築家、構造エンジニア | 建築家、構造エンジニア | 建築家、修理業者 |
| 助成金/補助金 | 地域によって提供 | 地域によって提供 | 一般的に補助が提供されない |
住宅ローン控除や融資といった経済的対策
耐震工事についての住宅ローン控除や融資は、住宅所有者が自宅を耐震化するためにかかる費用を軽減するための経済的支援措置です。これらの対策は国や地域によって異なりますが、以下は一般的な経済的支援に関する情報です。
耐震工事ローン
一部の地域では、住宅所有者が耐震工事に必要な資金を借りるための特別な耐震工事ローンプログラムを提供しています。これらのローンは低金利で、耐震補強などのプロジェクトに資金を提供するために使用できます。
住宅ローン控除
耐震工事に費用がかかる場合、一部の国や地域ではこれらの費用に関連する住宅ローン控除を提供しています。住宅ローン控除は住宅ローンの一部または全額を所得税から差し引くことができる優遇措置です。控除の金額や要件は地域によって異なります。
助成金と補助金
一部の地域では、耐震工事に補助金や助成金を提供しています。これらのプログラムは、住宅所有者に耐震補強工事の一部費用をカバーするための補助を提供します。
エネルギー効率向上プログラム
エネルギー効率向上を含む住宅改修プロジェクトに関する補助金や融資プログラムが一部の地域で提供されています。これにより、住宅の耐震化と同時にエネルギー効率も向上させることができます。
地域ごとの支援
地域や自治体によっては、耐震工事のための地域独自の支援策が提供されていることがあります。地元の政府機関のウェブサイトや住宅所有者向け情報リソースを確認して、地域ごとの支援策について詳細を調査しましょう。
補助金・助成金制度の活用方法
耐震工事の補助金や助成金制度を活用するためには、以下の一般的なステップと注意事項に従うことが重要です。具体的な要件やプログラムは国や地域によって異なりますので、地元の政府機関や関連組織のウェブサイトで詳細な情報を入手しましょう。
①制度調査 参照 東京都耐震化助成制度
地元の政府機関、建設業界の団体、住宅関連の団体のウェブサイトを調査して、耐震工事に関する補助金や助成金制度についての情報を収集します。
要件の確認:
各プログラムには異なる要件があります。プログラムがどのような工事や改修に適用されるか、どの条件を満たす必要があるかを確認しましょう。これには、所得制限、住宅の年数、工事の種類などが含まれます。
②申請手続き
補助金や助成金を申請するために必要な手続きや書類を入手し、申請手続きを開始します。これには、申請書、証明書類、工事の詳細などが含まれます。
予算策定
補助金や助成金を受けるためのプロジェクト予算を策定しましょう。これには工事の詳細なコスト見積もりやプロジェクトのスケジュールが含まれます。
リフォーム会社などの協力
耐震工事は専門的な知識とスキルが必要です。建築家や構造エンジニアなどの専門家と協力し、工事の計画と設計を行います。
申請提出
補助金や助成金の申請書を完了し、必要な証明書類と共に申請を提出します。提出期限を守ることが重要です。
承認と監査
申請が受け付けられ、プロジェクトが承認された場合、工事を進めます。一部のプログラムでは工事中および完了後の監査が行われることがあります。
資金の使用
補助金や助成金をプロジェクトに適切に使用し、工事を完了します。
報告とアウトリーチ
必要なら、工事の進捗状況や費用の報告を行い、プログラム運営機関と連絡を取りましょう。
注意: 補助金や助成金プログラムは要件が厳格であり、申請プロセスに時間がかかることがあります。また、予算や工事の計画を正確に立て、条件を満たすようにすることが重要です。最新の情報や具体的なプログラムに関する詳細は、地元の政府機関や関連組織に直接問い合わせて入手することがおすすめです。
自治体の補助と助成金制度
自治体が提供する補助金と助成金制度は、地域ごとに異なりますが、耐震工事に関連するプログラムも存在します。以下は、一般的な自治体の補助金と助成金制度に関する情報です。具体的な情報は、お住まいの自治体のウェブサイトや地元の政府機関に問い合わせて入手することがおすすめです。
耐震補助金
一部の自治体では、住宅の耐震工事に対する補助金を提供しています。これには特定の工事に対する一部の費用の補助や助成金が含まれることがあります。
耐震診断補助金:
一部の地域では、住宅の耐震診断に対する補助金を提供しています。診断によって耐震工事の必要性が明らかになり、その後の補助金や助成金の申請に繋がることがあります。
耐震改修助成金
耐震工事に必要な改修に対する助成金プログラムも一部の自治体で提供されています。これにより、工事費用の一部をカバーすることができます。
エネルギー効率向上プログラム
エネルギー効率を向上させる改修工事に対する補助金や助成金が提供される場合もあります。これにより、エネルギー効率向上と耐震補強を組み合わせて実施できます。
低所得者向け支援
一部の自治体では、低所得者世帯に対する住宅改修プログラムが提供されており、耐震工事に関連する補助金や助成金を受けられる場合もあります。
自治体のウェブサイト
補助金や助成金の詳細情報、要件、申請手続きなどは、地元の自治体のウェブサイトで提供されることが多いです。こちらで詳細を確認しましょう。
申請方法と対象者の条件
申請方法
ウェブサイト
お住まいの自治体のウェブサイトで、補助金や助成金プログラムに関する情報を探します。ウェブサイトから申請フォームや必要書類をダウンロードできることがあります。
申請書の記入
補助金や助成金のプログラムに応じた申請書を記入します。申請書にはプロジェクトの詳細、予算、工事の範囲、所有者情報などが含まれます。
必要書類
申請に必要な証明書類や書類を提出します。これには証明書、診断結果、予算見積もり、建物の情報などが含まれます。
提出期限
申請書および必要書類の提出期限を守りましょう。期限を逃すと申請が受け入れられないことがあります。
審査と承認
提出された申請は審査され、承認されるかどうかが決定されます。審査には一定の時間がかかることがあります。
プロジェクトの実施
承認が得られたら、工事を進めます。一部のプログラムでは工事中および完了後の監査が行われることがあります。
報告
補助金や助成金プログラムによっては、工事の進捗状況や費用の報告が必要な場合があります。
対象者の条件
対象者の条件はプログラムによって異なりますが、一般的な条件には以下のようなものがあります:
住宅所有者
ほとんどのプログラムは住宅所有者が対象です。借家や賃貸住宅の所有者は通常対象外です。
住宅の年数
耐震工事プログラムによっては、特定の建築年数の住宅に限定されることがあります。新築住宅や一定の年数以上経過した住宅が対象になることがあります。
所得制限
一部のプログラムは、所得制限を設けて低所得者向けに提供されます。所得証明書が必要な場合もあります。
工事の種類
補助金や助成金のプログラムは、特定の工事や改修に適用されることがあります。耐震工事に関連する改修や工事が対象です。
申請書の作成方法と交付条件
申請書の作成方法
ウェブサイトで情報収集: お住まいの自治体のウェブサイトで、補助金や助成金プログラムに関する情報を収集します。プログラムの詳細や申請書類のダウンロード先を見つけましょう。
申請書の取得
プログラムに関連する申請書類を入手します。これらのフォームは通常ウェブサイトからダウンロードできます。
申請書の記入
申請書に必要な情報を入力します。これにはプロジェクトの詳細、所有者情報、予算、工事のスケジュールなどが含まれます。フォームの指示に従って記入しましょう。
必要書類の添付
申請に必要な証明書類や書類を収集し、申請書に添付します。これには診断報告書、予算見積もり、建物情報などが含まれます。
提出期限の確認
申請書類の提出期限を確認し、期限内に提出しましょう。期限を逃すと申請が受け入れられないことがあります。
申請書の提出
申請書類と必要書類を指定された方法で提出します。提出方法についてはプログラムのガイダンスに従ってください。
交付条件
補助金や助成金のプログラムには、通常、特定の条件が付いています。これらの条件はプログラムによって異なりますが、一般的な条件には以下のようなものがあります:
工事の完了
補助金や助成金は、工事が完了した後に交付されることが一般的です。工事が予定通りに完了し、プログラムの要件を満たす必要があります。
監査
一部のプログラムでは、工事中および完了後に監査が行われることがあります。プロジェクトが要件を満たしているかどうかを確認するための措置です。
予算の遵守
補助金や助成金を使用する際には、予算内で費用を抑え、予算の遵守が求められることがあります。
報告
一部のプログラムでは、工事の進捗状況や費用に関する報告が必要なことがあります。報告が要求された場合、期限内に提出することが必要です。
適格な工事
補助金や助成金は、特定の種類の工事や改修に対して提供されることがあります。プログラムに含まれる工事の種類に従うことが必要です。
事例とリフォーム・改修計画の策定
耐震改修工事の事例紹介
事例1: 一戸建て住宅の耐震工事
所在地: 東京都台東区
建物の年数: 築40年
補助金プログラム: 台東区の助成金プログラム200万円を使用
工事の内容: 基礎補強、柱・梁の強化、耐震補強壁の設置
予算: 約2,000,000円
無料診断の申し込み方法
ファミリー工房では耐震チェックを無料診断しております。
お気軽にお問合せ下さい。⇒こちら
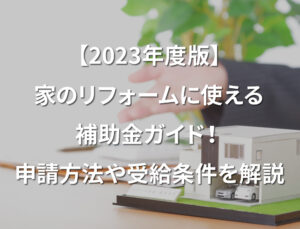
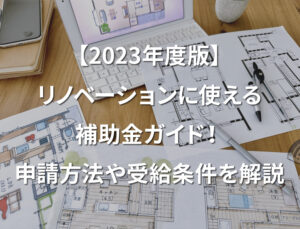
まとめ
耐震工事は日本の住宅所有者にとって非常に重要な懸念事項です。地震の発生が予測されている地域では、耐震補強が急務となります。30年以内に巨大地震が来る可能性が高まっている中で、早めの対策がより重要になります。
耐震補強に関して、補助金や助成金の活用も検討できます。日本の自治体や政府は、住宅所有者に対して耐震工事の費用を一部支援するプログラムを提供しています。このようなプログラムを利用することで、費用を抑えながら住宅の耐震性を向上させることができます。
ファミリー工房では、お客様が安全な住環境を確保し、将来の地震に備えるお手伝いをさせていただきます。耐震補強の相談やプランニングから助成金の申請まで、専門のチームがお客様のニーズに合ったサポートを提供します。
お住まいの地域や建物の状態に合わせて最適な対策を見つけ、地震に対するリスクを軽減しましょう。ファミリー工房はお客様の安全と快適さを第一に考え、お手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。
- 監修者
- 吉澤 理都
Chief
【保有資格】
・一級建築士
・監理技術者
・既存住宅状況調査技術者


〒120-0001 東京都足立区大谷田 4-1-20 1F
JR線・東京メトロ千代田線「北綾瀬駅」下車 徒歩7分
営業時間
10:00~18:00 / 定休:毎週日・月
※夏期休暇、年末年始休暇、ゴールデンウィークを除く







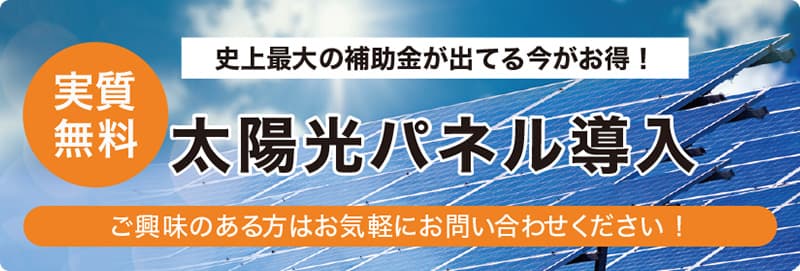
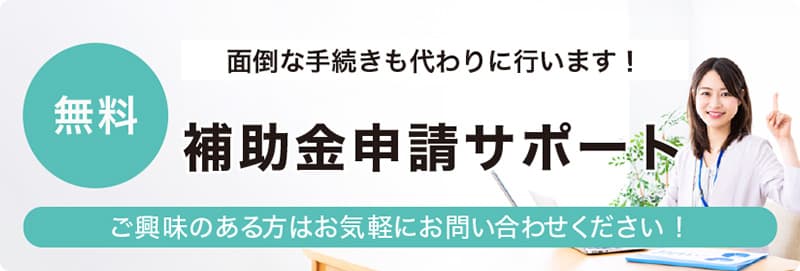
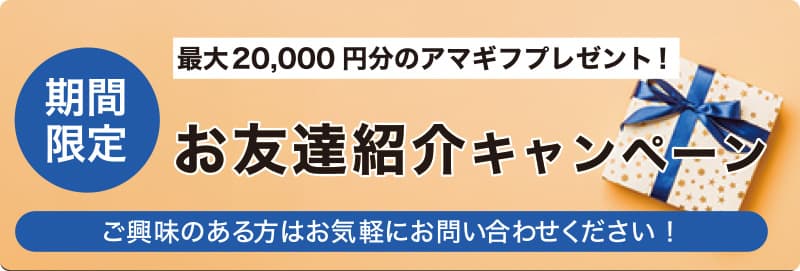
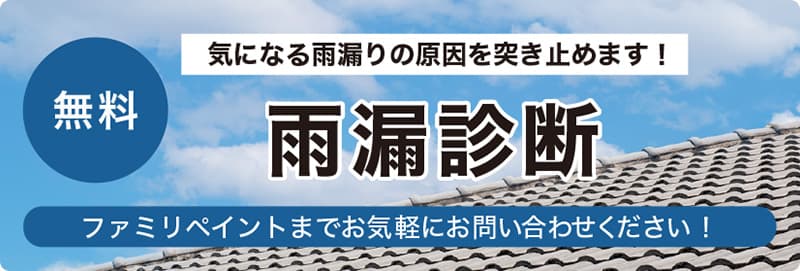
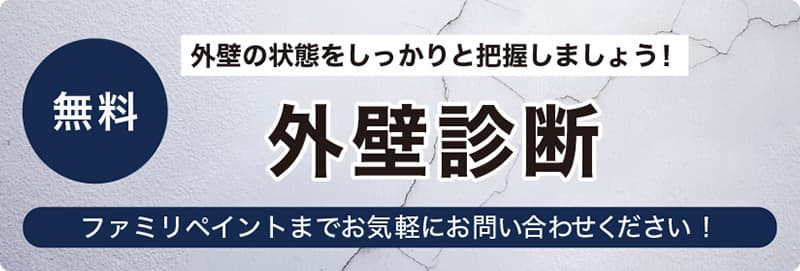
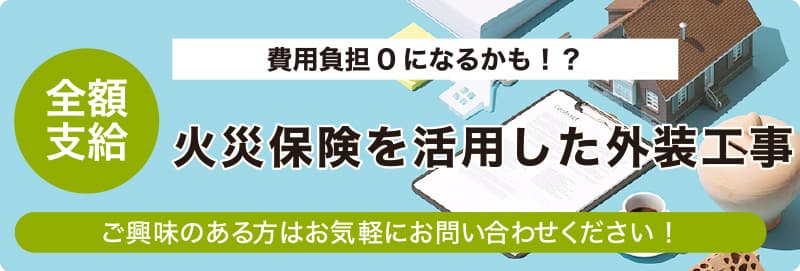




きめ細やかな視点で、お客様の生活に寄り添った提案を行います。
まずは気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いします。